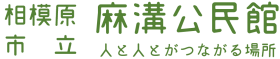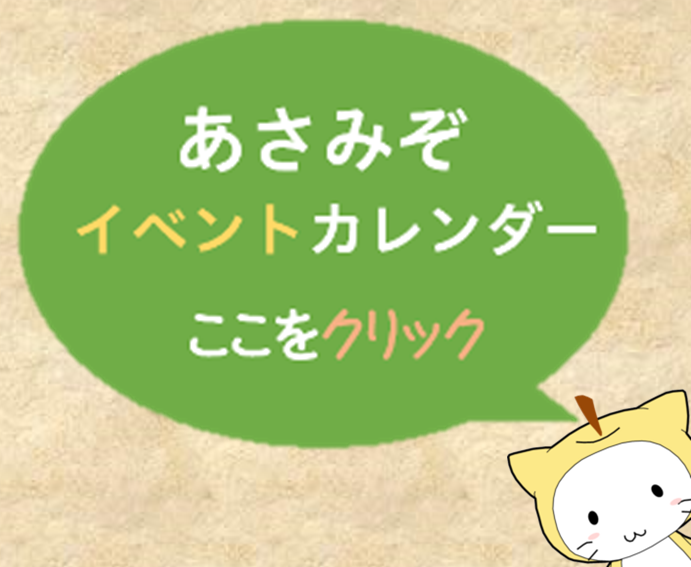酒まんじゅうづくり講習会
7月23日(火)、24日(水)の2日にかけて、「ふるさとの味を伝える会」の
方々を講師に招き、毎年恒例となっている文化部主催の酒まんじゅうづくり
講習会が行われました。
「相模原では昔から夏になるとどこの家庭でも酒まんじゅうを作りました。
初夏から秋にかけての季節、夏祭り、お盆、お月見と手作りの酒まんじゅうは
大変なご馳走でした。お祭りにはお客様を迎える前に必ず親戚へ配ったり
するものでした。また、相模原は地形がほとんど台地で田んぼがあまりありません。
主食の米は貴重な存在でした。そこで、米の代用食として畑でとれる小麦を利
用して何か作れないか……と言う事で酒まんじゅうとうどん等をつくるよう
になり、特に近年は相模原の名物として酒まんじゅうが皆さんに大変ご馳走として喜ばれるよう
になりました。」(引用:酒まんじゅうづくり講習会の資料)
参加者は17人で、3つの班に分かれて、1日目は、酒まんじゅうの酒仕込みと
みそあん作りの講習を行いました。酒仕込みでは、「こうじ」が多すぎると、
まんじゅうがかたくなるとのことでした。2日目は、酒まんじゅう作りの講習
を行いました。講師の話では、「1次発酵、2次発酵の見極めは、室温、湿度
などの微妙な環境で変わってくるので、言葉で表現するのがむずかしいです
ね、まずは自分で作ってみて、後は経験を重ねてですね」とのことでした。
参加者からは、「みそ味が美味しかったです」「出来上がりで2倍に膨らんだ
まんじゅうを見て感動しました」「先生が班ごとについて下さり、小さな疑問
もすぐに教えて頂き、とても理解ができました」などの感想がありました。
「ふるさとの味を伝える会」の皆さんありがとうございました。
文化部の役員の皆さん、お疲れ様でした。
(取材:ホームページ編集委員)
-

<1日目>酒まんじゅうの酒仕込み -

<1日目>みそあん作り -

<2日目>生地作りの説明 -

<2日目>1次発酵後、小分けにします -

<2日目>手前が2次発酵した後の生地 -

<2日目>あんのつめ方を説明しています -

<2日目>生地にあんをつめます -

<2日目>ほら、蒸しあがったよ -

<2日目>最後に皆さんで試食タイム