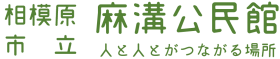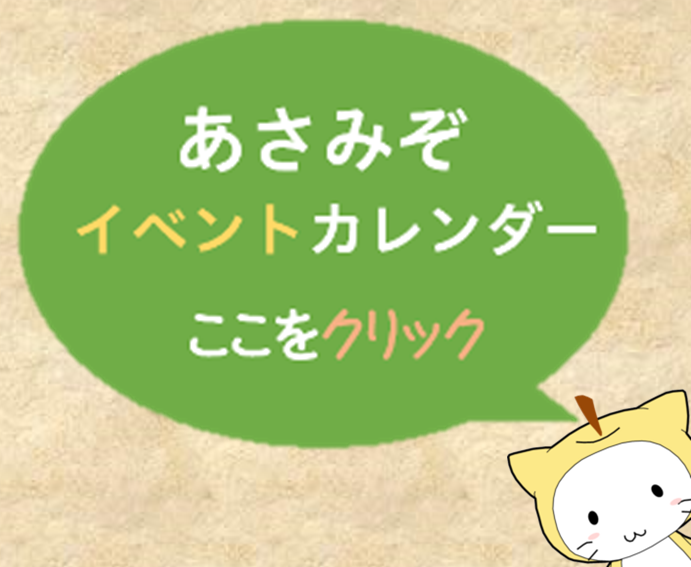しめなわづくり講習会
12月1日(日)、シルバー人材センターの山口氏を講師にお招きし、毎年恒例となっ
ている文化部主催のしめなわづくり講習会が開催されました。
作り方を習得して卒業された方もいるようですが、今回は初めて参加する方が大半で、伝統文化への関心の高まりを感じます。
最初に、はかまになる稲穂飾りを作りました。次に輪っかになる部分を作るのですが、
輪っかの大きさが15センチくらいにするのがポイントだそうです。
それが終わると、今度は、はかまになる3本の稲穂を輪っかに差し込んで、65センチくらいになるようにしたら、3本の稲穂を結びます。
さらに、輪っかを真円にして結んだ稲穂の一番上と輪っかを結び稲穂飾りを作ります。
最後に、だいだい(みかん)、宝袋、寿センスなどの飾り付けをして完成です。
なかなか上手くいかなくて、講師の方やサポーターの方に手助けしてもらう場面もあり
ましたが、講師の方がほめてくださるほど、立派なしめなわを完成させることができ、
良い年を迎えられそうです。
~「お正月飾りって、いつから?いつまで?飾る時期は?処分方法は?」~
(お正月飾りを飾る時期)
お正月飾りは12月28日までに飾りましょう。
(地域や宗派、ゴロ合わせによっても変わってきます。)
29日~31日がいけないとする理由
29日 「苦に通じる」というゴロ合わせになります。
30日 「旧暦の大晦日」と同じことになるが、
現在はこの日に飾る方が増えています。
31日 「一夜飾り」でお葬式と同じような意味合いになります。
(飾っておく期間)
年神様がいらしゃる期間「松の内」まです。
松の内は一般的に元旦から7日までです。
(地域によっては違いがあります。)
鏡餅は11日の鏡開きまで飾っておいても良いとされています。
(処分の仕方)~正式版~
1月15日の小正月に神社などで行われる火祭り「どんと焼き」「左義長」で
焼きます。この火で焼いたお餅を食べると無病息災になると言われています。
*最近では境内でのどんと焼きは環境問題などにより少なくなってきています。
(処分の仕方・捨て方)~自宅版~
新聞紙を広げて、その上にお正月飾りを置き、お塩を左・右・左と3回かけます。
その後、新聞紙にくるみ、処分して下さい。
===講習会資料引用===
(取材:ホームページ委員)
-

下段の稲穂飾りをつくっています -

しめなわの輪っかになる部分を作っています -

輪っかになるようにひもで結んでいます -

輪っかと稲穂を合体させています -

しめなわ飾りの下ごしらえをしています -

しめなわの飾り付けもうすぐ完成します
-

各自作成したしめなわを持って集合写真です